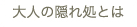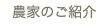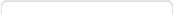
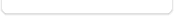

HOME > 地方・自然の紹介コーナー
散歩
○静岡県御前崎市佐倉
○東京都国分寺市
お鷹の道
◆お鷹の道の由来 東京都の西、武蔵野の面影が残る辺りには、国分寺崖線(がいせん)と言われる、武蔵野台地を多摩川が浸蝕して出来上がった、30kmもの距離に及ぶ段丘があります。そして、国分寺崖線から流れ出た湧き水を水源として小川が生まれ、その小川沿いに遊歩道が作られています。江戸時代、国分寺付近は尾張徳川家のお鷹場だったことから、この遊歩道はお鷹の道と名付けられています。 ◇写真その1 ・その昔、不治の病に冒された玉造小町と言う美しい姫が池の水を浴びたところ、病が治癒したと言い伝えられているのが、この真姿の池です。 ◇写真その2 741年、聖武天皇の詔によって、国ごとに官寺が建てられました。これが国分寺ですが、遊歩道を抜けたすぐ右手に在るこの最勝院国分寺は、1333年に元のものが戦火で焼失してしまった為、その後江戸時代になって再興されたもので、境内には万葉植物園があります。 ◇写真その3 国分寺崖線から湧き出た、清流とも言うべき澄みきった清水が小川となって流れています。 ★この遊歩道は、 国分寺公園と隣接して(野鳥の森)います。 また、農家の直販所や伝統を感じる蔵などがあり、実に良い遊歩道です。また名水百選に選ばれた小川は、ホタルの生息地として大切に管理されています。カワニナや川魚やザリガニと出会う事もあります。 くれぐれも大声をだしたり、カワニナをとる行為はやめましょう!
◆お鷹の道の由来 東京都の西、武蔵野の面影が残る辺りには、国分寺崖線(がいせん)と言われる、武蔵野台地を多摩川が浸蝕して出来上がった、30kmもの距離に及ぶ段丘があります。そして、国分寺崖線から流れ出た湧き水を水源として小川が生まれ、その小川沿いに遊歩道が作られています。江戸時代、国分寺付近は尾張徳川家のお鷹場だったことから、この遊歩道はお鷹の道と名付けられています。 ◇写真その1 ・その昔、不治の病に冒された玉造小町と言う美しい姫が池の水を浴びたところ、病が治癒したと言い伝えられているのが、この真姿の池です。 ◇写真その2 741年、聖武天皇の詔によって、国ごとに官寺が建てられました。これが国分寺ですが、遊歩道を抜けたすぐ右手に在るこの最勝院国分寺は、1333年に元のものが戦火で焼失してしまった為、その後江戸時代になって再興されたもので、境内には万葉植物園があります。 ◇写真その3 国分寺崖線から湧き出た、清流とも言うべき澄みきった清水が小川となって流れています。 ★この遊歩道は、 国分寺公園と隣接して(野鳥の森)います。 また、農家の直販所や伝統を感じる蔵などがあり、実に良い遊歩道です。また名水百選に選ばれた小川は、ホタルの生息地として大切に管理されています。カワニナや川魚やザリガニと出会う事もあります。 くれぐれも大声をだしたり、カワニナをとる行為はやめましょう!
○東京都国分寺市
○千葉県富津市金谷 (町並み)
珍しい’塀’
◆JRの浜金谷駅の周辺(路地)を紹介します。 1.駅を背にしての町並みです。(1枚目の写真) ・実に静かです。食道とラーメン屋さん等2,3件ありました。釣り道具屋さんも目の前にあります。 2.1枚目の写真の通りに沿って、10メートルほど歩き、左に左折して約15メートル程の民家の塀が、実に興味深いです。(2枚目の写真) 3.最初のとおりを真直ぐ20メートル歩くと車通りにでます。その手前の角に魚屋さんがあります。 自家製で干物をやっていました。 ・このとおりを右に右折して100メートルの所にフェリー乗り場があります。 この車通りにも食事をする場所があります。 チェーン店もあり、昼時は近所の主婦らしい方で混んでいました。
◆JRの浜金谷駅の周辺(路地)を紹介します。 1.駅を背にしての町並みです。(1枚目の写真) ・実に静かです。食道とラーメン屋さん等2,3件ありました。釣り道具屋さんも目の前にあります。 2.1枚目の写真の通りに沿って、10メートルほど歩き、左に左折して約15メートル程の民家の塀が、実に興味深いです。(2枚目の写真) 3.最初のとおりを真直ぐ20メートル歩くと車通りにでます。その手前の角に魚屋さんがあります。 自家製で干物をやっていました。 ・このとおりを右に右折して100メートルの所にフェリー乗り場があります。 この車通りにも食事をする場所があります。 チェーン店もあり、昼時は近所の主婦らしい方で混んでいました。
○善光寺(長野市)の表通りと裏通り
善光寺の散歩
◆2月18日 ・この日は、雪が少し舞い散る日でした。 観光の方は、少なく目を引いたのが外国からの観光客と合格祈願の学生さんでした。・・皆さん頑張って下さい。 ◇善光寺の紹介 善光寺(ぜんこうじ)は、長野県長野市元善町にある無宗派の単立寺院である。山号は「定額山」(じょうがくさん)。 山内にある天台宗の「大勧進」と25院、浄土宗の「大本願」と14坊によって護持・運営されている。「大勧進」の住職は「貫主」と呼ばれ、天台宗の名刹から推挙された僧侶が務めている。「大本願」は、大寺院としては珍しい尼寺である。住職は「善光寺上人」と呼ばれ、門跡寺院ではないが代々公家出身者から住職を迎えている。2010年(平成22年)現在の「善光寺上人」(「大本願上人」)は鷹司家出身の121世鷹司誓玉である。 ◇基本的な写真を紹介します。 ①1枚目の写真は、正面からの善光寺 ②2枚目の写真は、善光寺に繋がる表通り ③3枚目の写真は、善光寺の裏通りの一つです ・季節的には、2月で春の足音をまだ聞く事が出来ませんでしたが、商店街と善光寺が一体となった雰囲気のある場所でした。 ・春になり、気候が良くなるともっといろいろな裏通り見学が出来るのではと期待しています。 ・・・・・今回は、簡単な紹介まで。
◆2月18日 ・この日は、雪が少し舞い散る日でした。 観光の方は、少なく目を引いたのが外国からの観光客と合格祈願の学生さんでした。・・皆さん頑張って下さい。 ◇善光寺の紹介 善光寺(ぜんこうじ)は、長野県長野市元善町にある無宗派の単立寺院である。山号は「定額山」(じょうがくさん)。 山内にある天台宗の「大勧進」と25院、浄土宗の「大本願」と14坊によって護持・運営されている。「大勧進」の住職は「貫主」と呼ばれ、天台宗の名刹から推挙された僧侶が務めている。「大本願」は、大寺院としては珍しい尼寺である。住職は「善光寺上人」と呼ばれ、門跡寺院ではないが代々公家出身者から住職を迎えている。2010年(平成22年)現在の「善光寺上人」(「大本願上人」)は鷹司家出身の121世鷹司誓玉である。 ◇基本的な写真を紹介します。 ①1枚目の写真は、正面からの善光寺 ②2枚目の写真は、善光寺に繋がる表通り ③3枚目の写真は、善光寺の裏通りの一つです ・季節的には、2月で春の足音をまだ聞く事が出来ませんでしたが、商店街と善光寺が一体となった雰囲気のある場所でした。 ・春になり、気候が良くなるともっといろいろな裏通り見学が出来るのではと期待しています。 ・・・・・今回は、簡単な紹介まで。
○御前崎市宮内
○巣鴨地蔵商通店街
観光地だよね。
2013年5月、東京都巣鴨の地蔵商店通商店街に初めて、行ってみました。 ここは、観光地だ。 元祖、イチゴ大福・・・・せんべい屋が多い、大福などの和菓子店も多く、平日なのに人通りが多いです。 高岩寺では、テレビで見た耳かきのオーダーメイドをやるお兄さんがいた。 ブラブラしながら日本茶と大福はいいなあ! 大きな地蔵を紹介しよう。 六地蔵尊です。 江戸六地蔵尊の一つとして知られるこのお寺は、真言宗豊山派醫王山東光院眞性寺と申します。起立年代不詳。元和元年(1615年)境内には松尾芭蕉の句の石碑があります。大きな傘をかぶり、杖を持つお地蔵様。江戸の六街道の出入口に置かれ旅の安全を見守ってくれました。 (巣鴨は中山道の出入り口でした)関八州江戸古地図、江戸絵図ほか多くの文献から眞性寺界隈は交通の要として賑わっておりましたことが伝わっております。 終わり
2013年5月、東京都巣鴨の地蔵商店通商店街に初めて、行ってみました。 ここは、観光地だ。 元祖、イチゴ大福・・・・せんべい屋が多い、大福などの和菓子店も多く、平日なのに人通りが多いです。 高岩寺では、テレビで見た耳かきのオーダーメイドをやるお兄さんがいた。 ブラブラしながら日本茶と大福はいいなあ! 大きな地蔵を紹介しよう。 六地蔵尊です。 江戸六地蔵尊の一つとして知られるこのお寺は、真言宗豊山派醫王山東光院眞性寺と申します。起立年代不詳。元和元年(1615年)境内には松尾芭蕉の句の石碑があります。大きな傘をかぶり、杖を持つお地蔵様。江戸の六街道の出入口に置かれ旅の安全を見守ってくれました。 (巣鴨は中山道の出入り口でした)関八州江戸古地図、江戸絵図ほか多くの文献から眞性寺界隈は交通の要として賑わっておりましたことが伝わっております。 終わり